離婚公正証書、不倫の示談書・慰謝料請求書を作成したい方へ
専門行政書士による離婚公正証書、示談書等の作成支援
離婚公正証書の作成準備を始める
〔全国対応〕メール・電話だけでも安心してご利用いただけます
離婚契約に実績ある行政書士事務所
047-407-0991
受付時間 | 9時から19時(土日は15時まで) |
|---|
作成依頼に「迅速」対応します。
住宅とあわせて住宅ローンの返済方法も財産分与で整理します
住宅ローンと離婚
婚姻してから購入した住宅は、離婚時の財産分与で重要な対象財産になります。
そうした住宅の取り扱いを財産分与で整理するときには、住宅ローンの返済(離婚後に返済する者、その方法など)についての検討が必要になります。
離婚後に住宅の所有となる者(名義人)と居住者、住宅ローンを返済する者、登記名義変更の有無、住宅ローンを借り換える予定などについて、財産分与を含めた離婚条件の全体を踏まえて夫婦で確認して決めておきます。
そして、財産分与で定めた住宅と住宅ローンの取り扱いを離婚協議書、離婚 公正証書に作成しておくことは、離婚後のトラブルを回避するうえで大切になります。
離婚するときの住宅ローン
協議離婚するときに住宅ローンが残っている住宅の整理方法を財産分与で決めておくことは、離婚する夫婦にとって大事な整理課題の一つとなります。
財産分与で住宅を取得することは財産上のメリットとして大きいですが、それに合わせて住宅ローンを負担することになれば、大きな債務を長期に負うことになりますので、財産及びリスクの管理面から慎重に検討しなければなりません。
離婚に合わせて住宅を第三者へ売却して清算する対応が明快な整理方法となりますが、いくつかの選択肢がありますので、どうしても選択に迷うことになります。
また、住宅ローンの残債額が住宅の売却時評価額を超えているオーバーローンの状態にあることがネックとなって、すぐには住宅の売却をすすめられず、離婚できない夫婦もあります。
そして、住宅ローンを「連帯債務」「連帯保証」の契約で借り入れているケースでは、住宅ローンの返済者を決めるうえで銀行との協議が必要になることもあります。
なお、離婚の届出までに住宅に関する整理方法を確定できなくても、ある程度の方針を固めて離婚契約を交わし、先に離婚の届出を済ませてしまう夫婦もあります。
そうした対応では、財産分与について取り決めた事項を離婚 公正証書に記録し残しておくことが安全であると言えます。
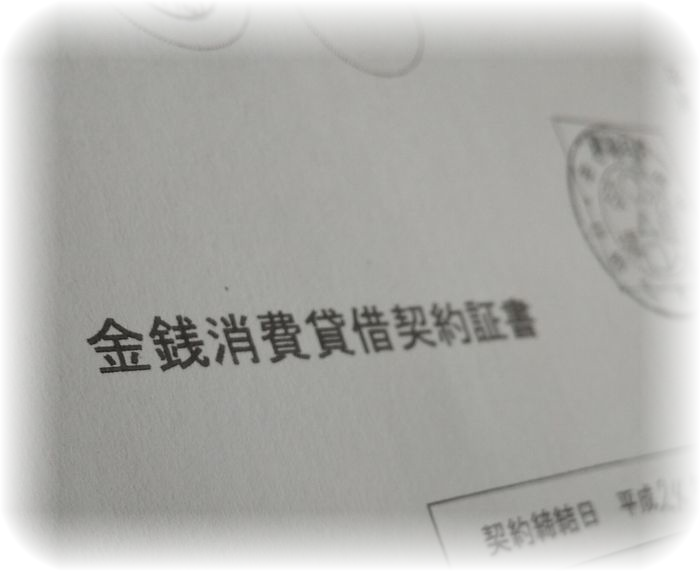
住宅ローンを借り入れるときには金融機関などと金銭消費貸借契約を交わします。
離婚時に重要な整理課題となる住宅ローン
結婚生活を送っている夫婦が住宅を購入するときは、どの夫婦も将来に離婚する可能性まで考慮せず、住宅金融支援機構、銀行、信用金庫など、金融機関から住宅ローンを借り入れることになります。
そして、夫婦で協力して住宅ローンを借り入れたり、両親から頭金の一部について贈与を受けるなど、少しでも希望に近い条件の住宅を購入すべく動くこともあります。
ところが、夫婦関係が上手くいかなくなって離婚する事態になれば、返済中の住宅ローンに関する整理がその夫婦が離婚をすすめるうえで最大の課題となることがあります。
もし、オーバーローンなどにあることで住宅ローンを整理できない状態にあると、それが可能となるまでは離婚することができないこともあります。
離婚することを決めた夫婦は、ローン付の住宅をどう整理するかに頭を悩ませることになり、ローン付の住宅は離婚条件の一つである財産分与で中心的な存在となります。
一般に住宅は生活環境面の基礎になるものであり、また、住宅ローンを負担することは経済面で大きなウェートを占めることになります。
住宅と住宅ローンに関する整理は、離婚後の生活に大きく影響する要素となります。
そのため、離婚の協議において住宅ローンの整理について適切に対処しておかないと、離婚後の生活が経済面でうまく回らない事態に陥らないことにもなりかねません。
夫婦が住宅ローン整理に適切に対処することの重要性を共に認識したうえで、住宅ローンの整理にしっかり取り組むことが大事となります。
当事務所においても、これまで多数の協議離婚の契約書作成に携わってきている中で、この住宅ローンの整理が夫婦を悩ませるやっかいな問題であると感じています。
そうした住宅ローンの整理をすすめるとき、次の2点を押さえて対応します。
- 「住宅ローン」と「住宅」を、どのように財産分与で配分するか?
- 決めた財産分与を実現するため、それを離婚契約書にどう定めるか?
この2点について、以下に検討していきます。
どうちらが住宅を取得し、どちらが住宅ローンを返済するか?
夫婦で購入した住宅は、その登記上の名義(所有者の表示)がどちらか一方の単独名義であっても、原則として夫婦の共同財産となり、普通は一緒に居住しています。
けれども、離婚によって別居することになるので、一方が住宅に継続して居住するか、第三者に住宅を売却するか、話し合って決めることになります。
もし、どちらか一方が住宅を取得することになれば、あわせて住宅ローンの返済義務も負うことが普通に見られる形ですが、それと異なる決め方をすることもあります。
また、住宅を第三者へ売却するときは、その売却代金で住宅ローンを全て返済します。
こうした決め事をするときは、住宅の評価額と住宅ローンの残債額または住宅ローンの契約形態(連帯債務、連帯保証)によって対応できる範囲も変わってきます。
財産分与における住宅の評価
協議離婚するとき、夫婦の共同財産を清算する「財産分与」について話し合います。
婚姻していた期間が長くなるに連れて、共同財産(預貯金、生命保険、住宅、自動車、各ローンなど)が形成されていきます。
財産分与の基本は「プラス財産」(財産として価値のあるもの)について配分を決めることになります。
ただし、借入金、住宅ローンなどの「マイナス財産」があれば、それらの借入金などについても、財産分与の中で清算することが実務上の取り扱いになっています。
一般的な考え方として、「プラス財産ーマイナス財産」の差引額(残額)を財産分与の対象として夫婦間で清算(配分)します。
これがプラスになるときは財産分与の対象財産が存在しますが、マイナスになるときは債務を負担(返済)する割合などを取り決めなくてはなりません。
この計算中に住宅ローンが含まれるときは、マイナスとなったときにその金額が大きくなることもあり、それをどのように整理するかということが問題となります。
一般に勤労者世帯では住宅の購入に際して住宅ローンが利用されており、比較的に長期(20〜35年)の償還期間(住宅ローンが完済されるまでの期間)を設定します。
また、夫婦共に働いている家庭も多いことから、金融機関から住宅ローンを借り入れるときに、夫婦が連帯債務者となって契約したり、夫が債務者名義となって妻を連帯保証人にしているケースが少なくありません。
このように夫婦で共同して住宅ローンを借り入れると、全体でレバレッジ(信用によるテコの原理)が大きく効いて高額な資金を調達することが可能になります。
しかし、離婚をすることになると、これが反対に問題化してしまうこともあります。
高額な住宅ローンを組んだときは、住宅の購入時から当分の間、住宅の時価評価額よりも住宅ローンの残債額が大きくなっているオーバーローンの状態になります。
オーバーローンであると、住宅の売却をするときに超過した債務を埋めるための資金が必要となるために、事実上で住宅を売却することが実行できなくなります。
オーバーローンにある住宅ローンに関して夫婦で返済する配分をどう定めるかということは、住宅ローンの借り入れ契約を踏まえて整理方法に悩むことになります。
夫婦で住宅ローン契約をしているケースでは、離婚の成立に伴って夫婦関係は解消されても、住宅ローン契約の負担にかかる関係を解消できないことも起きてきます。
「住宅の売却」と「離婚後における住宅の利用」
住宅の所有権すべてを財産分与として夫婦のどちらか一方だけに持たせて住宅を整理する方法は、とられることが多くあります。
共有することも理論上は可能ですが、離婚して別々に生活をする他人同士が維持管理に手間とお金がかかる不動産を共同管理することは望ましい形と言えないからです。
また、不動産価格の上昇が見込めなくなった現在では、使用しない不動産の持分を持ち続けることにメリットはありません。(第三者へ売却するときは除く)
そのほか、離婚する前後の時期に住宅を第三者へ売却して金銭に換えたうえで、それを夫婦間で配分する整理も多くとられます。
住宅を現金に換えて清算する方法は、所有者、住宅ローンの返済義務者を決めなくても整理できますので、住宅と住宅ローンをシンプルに整理することができます。
しかし、住宅を金銭に換える方法は、オーバーローンの状態にある住宅では、売却時にマイナス分を補充する資金を準備できないと、選択することができません。
住宅を換価するために住宅の売却代金を充当しても足りない住宅ローンの残債すべてを清算する資金は、一般に多額なものになるからです。
住宅ローンを利用していながら、手持ち資金が潤沢にある家庭は滅多にありません。
ただし、住宅を売却するときの不足金が大きくなければ、手持ち資金を充当することでローン付住宅を第三者へ売却することもできます。
なお、住宅は財産として評価するだけでなく、家族が生活する本拠としての側面もありますので、住宅の売却に対し心理的に抵抗感を持つことも少なくありません。
とくに、住宅を生活の中心に置いて幼い子どもを育てている妻にとっては、住宅に対する思い入れが夫より相当に強くあり、できれば離婚した後も継続して住宅に住み続けたいと考えることが多くあります。
離婚してからも住宅ローンを返済してくことが可能であれば、住宅を売却しないまま、夫婦のどちらか一方が住宅に住み続けることができます。
このとき、住宅の所有者と利用者が同一となればわかりやすい整理方法となりますが、両者が異にして整理する方法もあります。
離婚した後に住宅の所有者とならない側は、他方側から住宅を賃借または無償で借りることになります。
このように、「住宅を売却するか」又は「利用するか」の選択に大きく分かれます。
決めたことを実現するために
離婚する際に夫婦で話し合って住宅、住宅ローンの取り扱いを決めたなら、それを着実に実現させることが大切になります。
約束を絵にかいた餅に終わらせてしまっては、離婚した後に二人の間でトラブルとなってしまい、最終的に二人が裁判所へ出向くことにもなりかねません。
裁判所で解決することになると、長い期間と弁護士費用の負担が重くかかってきます。
とくに、住宅、住宅ローンは金額の大きなものであることから、万一問題の解決に失敗したときに受ける損害額は大きなものとなります。
夫婦で取り決めをするときには、大事な条件を明確にして、それを実現させる手続きを双方で約束し、その約束したことを離婚協議書、離婚 公正証書に定めておきます。
そうした過程を慎重に対応しておくことで、離婚後のトラブル回避に役立ちます。
なお、離婚協議書は個人で作成することもあり、そのときは、取り決めたことが明確となるように重要な事項をもれなく離婚協議書に記載しておきます。

住宅ローンの残債があるときは、財産分与の整理が離婚手続において難しい課題になります。
住宅ローンを借りた金融機関との協議・調整
離婚する際にローン付住宅を整理することが難しくなる理由の一つとして、夫婦だけでは整理の方法を確定させることができず、住宅ローンを借り入れた金融機関などと契約の変更等に関して協議又は調整することが必要になることがあります。
金融機関としては、住宅ローン契約を結んだ夫婦が離婚することになった後も、契約どおりに住宅ローンを全て返済してもらわなければ困ります。
支払いが滞れば住宅を競売にかけることも可能ですが、そうした面倒な手間をかけずに貸したお金の全額を回収したいと考えます。
そのため、金融機関又は保証会社は、自分側に不利となる変更契約には応じません。
夫婦から離婚になることを理由として住宅ローン契約を変更したいと金融機関に申し出ても、その要望に金融機関が応じるかは条件次第となり、はっきり分かりません。
ただし、金融機関は、住宅ローン債権の保全に支障の生じない範囲で対応できる方法があれば、契約条件の変更を認めることがあります。
もし、柔軟に対応しなければ、債務者が住宅ローンをほかの金融機関に借り換えてしまうこともあり、期待していた利息収入を得られなくなるからです。
住宅ローン契約における「連帯債務」又は「連帯保証」の解消
離婚した後にも元夫婦の間に住宅ローン契約について連帯債務または連帯保証の義務が続いていくと、経済的には一蓮托生の関係が継続することになります。
経済的つながりを残してしまうことは、二人の関係を完全に解消できたことにならず、離婚したときの望ましい形と言えないことは明らかです。
離婚後に住宅ローンを返済する義務は、通常では住宅を取得する側が引き受けます。
そこで、夫婦としては、住宅の財産分与にあわせて、連帯債務または連帯保証の関係を解消させ、一方だけに住宅ローン債務の負担をまとめる契約変更をしたいと考えます。
しかし、住宅ローンの貸主である金融機関は、夫婦二人を合わせた返済力を条件として住宅ローンを貸したにもかかわらず、それを一人だけの返済に変更することは住宅ローンを返済する力が落ちてしまい、延滞の発生するリスクが高まると考えます。
金融機関は、連帯債務または連帯保証を解消することを容易には認めてくれません。
そこで、金融機関と話し合う中では、住宅ローン契約を結んだ時点と比較して返済力が高まっていること、住宅ローン契約に対して代わりの連帯保証人または追加担保を提供することなど、金融機関が安心できる情報、条件を提示することが求められます。
住宅ローンの返済が進行したことで残債額が減っていたり、離婚後の返済者となる側に十分な収入等の資力があれば、金融機関が契約変更を認めることもあります。
債務者の名義を変更すること
夫が妻に対して財産分与として住宅を譲渡することになれば、夫は、住宅ローン契約の債務者の名義も夫から妻へ変更したいと望みます。
自分で所有しない住宅に付いている住宅ローンを返済していく義務だけを負うことは、夫にとって何の得にもならないからです。
しかし、返済中である住宅ローンの債務者を途中で変更することは、債権者にとっては住宅ローンを新たに貸し付けることに近い意味を持ちますので、妻に住宅ローンを返済できる十分な資力が備わっていなければ、金融機関は債務者の変更を認めません。
ただし、住宅ローンの借り入れ時から年数が経過して残債務が少なくなっており、妻に安定した給与収入等があれば、金融機関が借り換えを認めることもあります。
一方、親族の間で住宅を譲渡するときに住宅ローンを借り換えることに否定的な姿勢を示す金融機関もあります。
住宅の所有者名義の変更については、金融機関ごとに個別の判断をしますので、実際に金融機関に変更を申し出てみなければ、その結果は分かりません。
住宅の(所有者)登記名義を変更すること
財産分与を原因として住宅の所有権を夫から妻へ移転することになれば、原則としては登記の名義も同時に変更しなければなりません。
不動産の登記は実態を表していることが望ましいためです。
そして、住宅の所有者となる側は、ただちに登記の名義を自分へ変更しておかないと、登記上で所有者になっている者が住宅を第三者へ売却してしまうことを心配します。
しかし、住宅ローン契約では、住宅ローンが完済するまでに住宅の権利を変更するときは金融機関の事前承諾が必要になっています。
この契約に違反して金融機関の承諾を得ないで住宅の所有者名義を変更してしまうと、契約違反を理由に住宅ローンの一括返済を求められる恐れがあります。
なお、住宅の登記名義を変更しても、その事実がすぐに金融機関に知られるとは限りませんが、そうした事態になることを心配することもあります。
このため、住宅ローンを返済中のときは、金融機関から承諾を得たうえで登記するか、金融機関に報告をしないまま変更してしまうかを判断することになります。
住宅ローンの借り換え
離婚することで住宅ローンを返済していく側となったことで、住宅ローンの借り換えを検討することもあります。
住宅ローンを借り換えるタイミングは、離婚前後の時期で考えられます。
ただし、十分な返済能力を備えてから借り換え手続きをすすめるために、離婚から一定期間を経過した時期に借り換えを予定する方もあります。
離婚後における経済面における生活設計をしっかり立て、住宅ローンの返済負担にも余裕を持つことも大切になります。(借入返済シュミレーション(全国銀行協会))
住宅ローンの借り換えには、金融機関の審査を受けて通過しなければなりません。
金融機関ごとに審査の基準は異なりますので、実際に金融機関に申し込みをしてみなければ、住宅ローンの借り換えが認められるかは分かりません。
そのため、複数の金融機関に並行して打診をしながら対応をすすめることもあります。
金融機関との協議には期間をみておきます
離婚することが決まると、そのために準備、整理しておかねばならないことについて急いで取り組み、手続きを早く完了させたいと考えるものです。
その際に住宅ローン契約を整理する方法について金融機関と協議をすすめるとき、少し期間を要することに留意しておかなければなりません。
金融機関に対して申し出る住宅ローン契約の変更内容によっては、金融機関側も社内等における検討、審査のために時間がかかります。
金融機関の担当者も契約変更の業務に慣れているとは限らず、すべてが期待どおりに進展するわけではありません。
住宅ローンの借り換えを検討するときは複数の金融機関に当たることもありますので、すべての金融機関から回答を得るまでには期間を見ておかなければなりません。
離婚に向けたスケジュールを考える際には、金融機関との協議にかかる期間を十分に見ておくと、気持ちにも余裕が持てます。
住宅とローンについて離婚契約に定める
住宅ローンと住宅に関する取り扱いを夫婦で取り決めたときには、それらを離婚協議書(離婚 公正証書)に定めておくことが手続きとして安全になります。
不動産の所有権者を明確にしておくほか、所有権移転登記の時期、登記費用の負担者、登記完了まで公租公課の負担などについても、契約として定めておきます。
離婚後に所有者とならない側が継続して住宅に居住することを夫婦で決めたときには、住宅の使用契約(賃貸借または使用貸借)を夫婦間で結んでおくことになります。
また、住宅ローンの実質的な負担者を変更するときは、離婚した後の住宅ローンの返済方法などを具体的に定めておくことが必要です。
このような取り決めを具体に整理したうえで離婚協議書に定めておくことで、離婚して年月が経過しても離婚時の取り決めを双方で確認することができます。
公正証書に定める
不動産の財産分与による譲渡、住宅ローン負担者の変更を含む離婚契約をするときは、公正証書による契約が利用されます。
公正証書を作成しなくても登記の手続きはできますが、離婚した後に当事者の間で万一トラブルが起きたときに備えて、重要な財産に関する取り決め事は公正証書契約が安全であると考えられています。
住宅ローンを完済した後に所有権移転登記又は財産分与による譲渡をするときは、実際の手続時期は離婚の成立日から相当に先の時期になりますので、安全な公正証書に合意した事項を記載しておくことが勧められます。
合意した財産分与の条件を公正証書に記載する際には、登記事項証明書、住宅ローンの契約書などによって住宅の所有権の態様、住宅ローンの契約形態を確認することで、権利関係を正しく把握しておくことが重要になります。
なお、公正証書契約は金銭の支払いについては強制執行できる執行証書になりますが、不動産の所有権移転登記ついては執行力を備えません。
東京の公証役場
離婚協議書との違いは?
離婚協議書は、協議離婚における夫婦間の取り決め事を確認する契約書になります。
そして、公証役場へ行かなくても、夫婦の間で離婚契約を成立させることができます。
急いで離婚の条件を取り決めて早く離婚届を出したい、二人で公証役場へ行く日程調整が難しい、あえて公正証書にしなくても大丈夫である、などの理由から離婚協議書を作成して離婚する夫婦も少なくありません。
契約としての効力は離婚協議書も変わりませんが、お金を支払う契約(財産分与、養育費、慰謝料など)については、公正証書のように支払い遅滞時に裁判をしなくて強制執行できることになりません。
離婚協議書に基づいて強制執行をするには、裁判の手続きを経なければなりません。
また、公正証書は原本が公証役場で長期に保管されますが、離婚協議書は契約した当事者が保管することになります。
そして、公正証書は、その記載内容について公証人が法律上で問題ないことをチェックして作成されますが、離婚協議書にはそうしたチェックが基本的に入りません。
そのため、離婚協議書を作成するには、法律知識を備えたうえで慎重に作成をすすめることが求められます。
登記費用の準備
財産分与を原因として住宅の所有権移転登記をする際は、登記費用が必要になります。
登記には、国へ納付する登録免許税が必要になるほか、登記手続きを司法書士へ依頼するときはその報酬支払いも生じます。
財産分与での登録免許税は、住宅の固定資産評価額の2パーセントになります。
住宅の所有権の持分全部を財産分与で譲渡するときは、意外に大きな金額となることに驚くでしょう。
このため、離婚が成立したら直ちに財産分与を原因として所有権移転登記をする場合、上記の登記費用をあらかじめ準備しておかなければなりません。
登記費用は、通常は権利者(住宅の所有者となる側)が負担しますが、夫婦の話し合いで折半したり、義務者が負担することもあります。
住宅ローンに関する離婚契約書の作成サポート
住宅と住宅ローンの整理を含めた離婚協議書(公正証書)を作成するサポートをご用意しています。
住宅の権利関係、住宅ローン借り入れの形態を踏まえて、離婚時における夫婦間の取り決めを離婚協議書として作成します。
ご利用料金は、契約する内容の難易度に関わらず一律であり、追加料金は生じません(プラン変更時は差額分が発生します)ので、最後まで安心してご利用になれます。
サポート期間内であれば、夫婦間の協議に応じて何度でも契約書を修正できますので、契約書の形を確認しながら着実に協議をすすめることが可能となります。
ご利用料金
離婚協議書の作成 (1か月間のサポート保証) | 3万4000円(税込) |
|---|
公正証書の原案作成 (1か月間のサポート保証) | 3万4000円(税込) |
|---|
離婚公正証書の作成 (3か月間のサポート保証) | 5万7000円(税込) |
|---|
上記のサポートは、ご住所地に関係なくご利用いただくことができます。
離婚公正証書を作成するサポートの詳細はこちら
銀行へ提出する離婚協議書も作成しています
銀行に対し住宅ローン契約の変更、住宅ローンの借り換えなどを申し込み、その調整がすすんでくると、銀行側から離婚協議書の提出を求められることがあります。
住宅ローンの貸付には審査におけるチェックポイントがあり、その一つとして財産分与によって住宅の権利が債務(予定)者に移転することを銀行側は確認します。
こちらでは、そうした離婚協議書の作成に対応してきておりますので、銀行等との対応で離婚協議書が必要なときにご利用いただくことができます。

「ご夫婦で決められた内容をチェックしたうえで、銀行等に提出できる離婚協議書を作成させていただきます。」
日本行政書士会連合会所属
特定行政書士 塚田章
県立柏高校、埼玉大学卒業
2013年行政書士事務所開設
住宅の財産分与では「登記」、住宅ローンの借り換え等については「住宅ローンの仕組み」を踏まえて整理の方法を検討しなければなりません。
しかし、整理の方法に間違いない正解というものはなく、ご夫婦それぞれの要望、事情などによって、最終的に一つの選択肢を選ぶことになります。
そうした判断の過程では、悩み、不安を伴います。
そして、ご夫婦の協議で整理の方法が決まったときにも、それらを離婚協議書にどのように契約として定めればよいものか悩むものです。
また、住宅ローンの借り換えを伴うときには銀行等から離婚協議書の提出を求められることもありますので、慎重な対応が求められます。
当事務所では、そうした住宅ローンが残っている住宅を含む財産分与に対応する離婚協議書を作成させていただきます。
離婚に際して大きな財産、債務の整理をすることになったときの対応を安心してすすめていただくことにお役に立てたら幸いであると考えます。
お問合せ・お申し込みのフォーム
ご記入をいただきまして「送信内容を確認する」ボタンをクリックください。
メールアドレスの入力に誤りがある場合、当事務所から返信することができませんので、慎重にアドレスをご入力ください。
そのほか、当事務所から返信がないときは、固定パソコンからの受信制限又はエラーが発生したと思われます。その場合は、お電話によりご確認ください。
また、返信メールの受信はできていても「迷惑ホルダー」等に分類されていることで、ご本人が返信を受けていることに気付かないこともあります。
※サポートのご利用に関係しない法律情報の確認又は照会、対応方法のご相談(アドバイスを求めること)には回答致しませんので、ご承知おきください。
メールへのご返事は、原則として24時間以内にさせていただいております。
24時間経っても返信のない場合、メールアドレスのご入力に誤りがあるか、サーバー側で迷惑メールに振り分けられていることが考えられます。
ご確認されてもお分かりにならない場合、お手数ですが、お電話でご確認くださいますようお願いします。
※docomo(ドコモ)、hotmail、gmail のアドレスへ送信できないことが多く起きています。
離婚時における住宅ローンのご相談について
離婚時における住宅ローン契約の変更、離婚協議書(公正証書)における条件の定め方などは、多くのご夫婦が戸惑う難しい課題となります。
そうしたことから、離婚契約における具体的な整理方法について無料相談で対応して欲しいとのご連絡をいただくこともあります。
しかしながら、住宅の財産分与と住宅ローンに関しての対応は、離婚時における財産状況、当事者の意向を踏まえながら複数の選択肢から選ぶことになるため、説明等の対応には時間を要します。
説明等によってご本人様が概要について理解しても、それからどう対応するか悩むことになり、直ちに解決の方法がみつかる問題ではありません。
そのため、整理方法を固めるには、ご夫婦で話し合いを重ねることになります。
当事務所の離婚協議書・離婚公正証書の作成サポートには、そうした住宅の財産分与に関するご相談、説明についてもサービスの一部として含まれています。
誠に申し訳ありませんが、住宅ローンのご相談、離婚協議書等の作成についてご相談を希望される方は、各サポートにお申し込みいだけますようお願いします。
離婚公正証書サポートのお問合せ
あなたの大切な離婚公正証書の作成について、養育費などの各条件の定め方、ご不明なことのご質問などにお答えしながら、専門行政書士が完成まで丁寧にサポートさせていただきます。
各サポートについてご質問などがありましたら、お気軽にメール・お電話ください。
離婚条件、金額等の具体的な定め方のご相談は、各サポートで対応させていただいてます。
047-407-0991
受付時間:9時~19時(土日:9時~15時)
離婚の公正証書、不倫・婚約破棄慰謝料の示談書作成支援
『サポート利用にご質問がありましたら、お問い合わせください。』
代表者:塚田章(特定行政書士)
日本行政書士会連合会所属
日本カウンセリング学会正会員
JADP認定上級心理カウンセラー
047-407-0991
〔受付時間〕平日9時~19時、土日9時~15時
公正証書・示談書などの作成を専門とする行政書士事務所です。
お問合せは、こちらまで
047-407-0991
営業時間
平日9時~19時
土日9時~15時
フォームのお問合せは24時間受付中
休業日
国民の祝日、年末年始
お急ぎのご依頼にも対応します。
事務所の所在地
千葉県船橋市本町1丁目26-14
サンライズ船橋401号
船橋駅徒歩4分(船橋シャポー側)

大きな通りの側道沿いにある建物「サンライズ船橋」の401号にあります。
メール・電話でも大丈夫です

「忙しく事務所へ行けない」という方にも、離婚の公正証書などの作成について、メールまたは電話により丁寧にサポートさせていただきます。


