離婚公正証書、不倫の示談書・慰謝料請求書を作成したい方へ
専門行政書士による離婚公正証書、示談書等の作成支援
離婚公正証書の作成準備を始める
〔全国対応〕メール・電話だけでも安心してご利用いただけます
離婚契約に実績ある行政書士事務所
047-407-0991
受付時間 | 9時から19時(土日は15時まで) |
|---|
作成依頼に「迅速」対応します。
離婚して縁を切りたい
離婚すれば、夫婦の身分関係は解消しますが、さらに二人の縁を完全に切りたいことを望む方もあります。
一方による不貞行為によって感情面でこじれて離婚になるケースでは、相手の顔すらも二度と見たくないという気持ちになる方もあります。
しかし、夫婦の間に未成年の子どもがいたり、共同して借り入れた住宅ローンを返済中であるときは、離婚をしても二人の関係を完全に縁を切るのが難しいこともあります。
縁を切れるか?
離婚して相手と完全に縁を切りたいと考えたときに、それが現実に可能となるかは、離婚の時における二人の状況によります。
離婚に際して二人の間で協議して定めておくことは、主に「子どもの監護」と「財産の清算」に関する事項になります。
そのため、夫婦に子どもが無く、財産について離婚時に完全に清算できるのであれば、離婚した後に二人の間に関わりが残ることはありません。
その反対に、夫婦の間に子どもがあれば、子どもが成人後に自立できるまでの監護に関して、二人には子どもの父母として関わりが残ります。
また、婚姻中に購入した住宅を離婚した後に売却して清算したり、住宅ローンの借入契約が夫婦の連帯債務、連帯保証になっているときは、それらの清算がすべて終わるまで関わりが続きます。
ただし、二人の間に関係が残ることがあっても、できるだけシンプルな関係にするよう離婚時に夫婦で取り決めておくこともできます。
なお、このときに子どもの監護について法律上の考え方に沿わない取り決めを二人でしても、その取り決めは無効となる恐れがあります。
また、財産面で返済中の住宅ローンについて、ローン契約と異なる取り扱いを夫婦間で決めても、その取り決めは事業者(銀行等の金融機関)に対しては通用しません。
このようなことにも注意して離婚時に夫婦で取り決め、必要に応じて離婚 公正証書を作成しておきます。
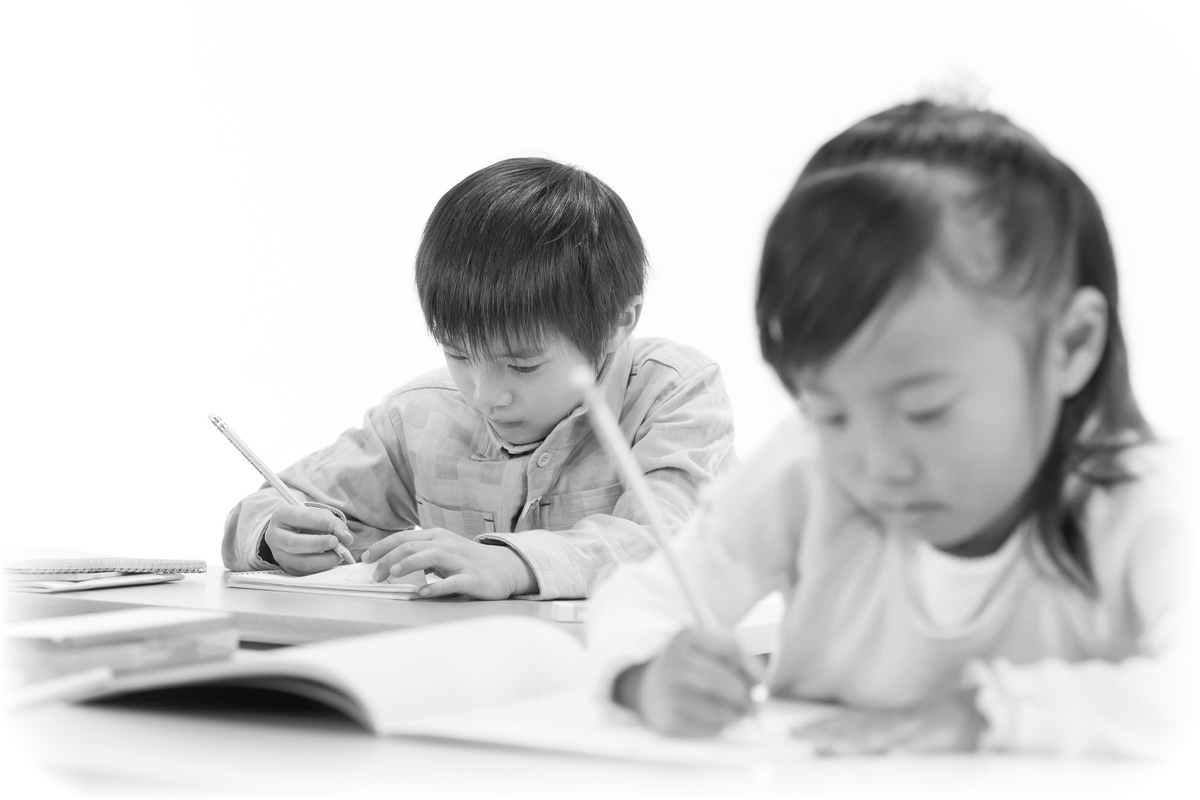
子どもがあれば、離婚をしても父母の関係は継続することになります。
子どもの監護について
夫婦の間に未成年の子どもがあるときは、協議離婚等で婚姻を解消しても、父母として子どもを扶養する義務は、子どもが自立できるまで引き続き負い続けます。
子どもが経済的に自立できるまで父母は子どもの監護養育にかかる費用分担する義務を負うことになり、非監護親から監護親へ養育費の名目で金銭が払われます。
こうしたことから、離婚しても普通には二人の関係を完全に切ることはできません。
ただし、監護の対象期間すべての養育費を離婚時に一括して払うことも可能であり、そうした方法で父母が関わる機会を大きく減らすこともできます。
また、養育費を払わない合意を父母間で行なうこともあり、こうした方法によっても、一括払いの場合と同様に父母の関わりを減らすことになります。
ただし、そうした父母間における養育費に関する合意が存在しても、その後に事情の変更が起きることで、合意した内容を見直しする余地が全く無いとは言い切れません。
たとえば、監護親の失業、病気などにで家計収入が途絶えたり、子どもが大きな病気にかかることで高額な治療費が必要になれば、合意していた内容では対応できないことも起こります。
こうしたときは、養育費の条件見直しを父母で協議して対応したり、家庭裁判所の調停又は審判を利用して条件の変更を確認することになります。
離婚後の非監護親と子どもの面会交流においても、離婚時に面会交流を実施しないとの父母間の合意があっても、その後に非監護親から面会交流の申し立てがあったときには家庭裁判所で面会交流を認める判断が示される可能性もあります。
面会交流の実施方法などは父母間で取り決めることになりますが、その過程では子どもの福祉を最優先することになっています。
財産の清算について
夫婦で作り上げた財産が離婚時に存在すれば、財産分与として夫婦で清算します。
預貯金など金融資産について清算する手続は、比較的に簡単です。
しかし、住宅については財産分与の対応では難しいこともあり、第三者に売却したうえでその代金を二人で配分するとなれば、売却が完了するまで期間がかかります。
また、オーバーローン住宅(売却時評価額<住宅ローンの残債額)であれば、離婚時における売却は事実上で行なうことができず、売却時期を将来に送らざるを得ません。
このように、住宅を売却して清算する時期が将来になるときは、それまでの間におけ住宅の使用、売却時の手続きなどを夫婦で決め、将来に再び接触する機会を持ちます。
住宅が共有名義となっており、離婚後に一方が住宅を使用し続けるときは、売却せず、一方を所有者として財産分与を定めます。
その時点で住宅ローンを返済中であると、金融機関の承諾を得なければ原則として所有権移転の登記をできませんが、将来に二人が関与することを避けるために移転登記を済ませてしまうこともあります。
住宅ローン 離婚の関係を整理することは条件によって対応が難しいこともあります。
もし、住宅ローン契約を夫婦の連帯債務又は連帯保証として金融機関と組んでいると、離婚時の対応として金融機関と夫婦の一方を契約から外す変更契約を結ぶか、ローンを完済しない限り、二人の関係は解消できません。
夫婦の間で住宅ローンの返済方法を離婚公正証書などで取り決めることも可能ですが、その内容については金融機関から承諾を得ない限り、住宅ローン契約上で二人の関与は継続します。
そのため、離婚した後に住宅ローンの返済が滞るような事態になれば、ローン契約上で債務者、連帯債務者又は連帯保証人になっていると金融機関から返済を求められます。
住宅ローンの取り扱いは金融機関との契約に縛られますので、夫婦二人だけでは離婚に合わせて完全に清算することができないこともあります。
このように財産関係においても、夫婦の財産事情によっては、離婚時に二人の関係を完全に切ることができないこともあります。
無理な契約をしないこと
以上のように、離婚することで二人の縁を完全に切りたいと考えていても、離婚時における夫婦の事情によっては、そうしたことが困難であることもあります。
離婚した後の関わりを断ちたい故に離婚の時に夫婦間で無理な取り決めをすることは、その後の履行面において何らかのトラブルが起きないとは限りません。
養育費を一切支払わず、又、面会交流を実施しないとの約束を夫婦で行なっても、離婚した後に困らずに生活できる保証はありません。
できるだけ望ましい条件の決め方としては、法律の趣旨を踏まえたうえで、標準型から大きく外れない取り決めをすることです。
異例的な取り決めをすることは、法律の効力面で問題の生じるリスクもあります。
また、子どもの監護養育が続くことになり、住宅に関する財産分与が未了となるにもかかわらず、離婚後の住所を相手に知らせたくないと考える方もあります。
しかし、二人の間における清算がすべて完了するまでの間は、互いに、相手の住所など連絡先を知っていないと困る事態が起きる恐れもあります。
可能にできる範囲内で二人の関与する機会を減らしたうえで、必要かつ最小限のことについては、相手に対し適切に対応しなければなりません。
離婚公正証書サポートのお問合せ
あなたの大切な離婚公正証書の作成について、養育費などの各条件の定め方、ご不明なことのご質問などにお答えしながら、専門行政書士が完成まで丁寧にサポートさせていただきます。
各サポートについてご質問などがありましたら、お気軽にメール・お電話ください。
離婚条件、金額等の具体的な定め方のご相談は、各サポートで対応させていただいてます。
047-407-0991
受付時間:9時~19時(土日:9時~15時)
離婚の公正証書、不倫・婚約破棄慰謝料の示談書作成支援
『サポート利用にご質問がありましたら、お問い合わせください。』
代表者:塚田章(特定行政書士)
日本行政書士会連合会所属
日本カウンセリング学会正会員
JADP認定上級心理カウンセラー
047-407-0991
〔受付時間〕平日9時~19時、土日9時~15時
公正証書・示談書などの作成を専門とする行政書士事務所です。
お問合せは、こちらまで
047-407-0991
営業時間
平日9時~19時
土日9時~15時
フォームのお問合せは24時間受付中
休業日
国民の祝日、年末年始
お急ぎのご依頼にも対応します。
事務所の所在地
千葉県船橋市本町1丁目26-14
サンライズ船橋401号
船橋駅徒歩4分(船橋シャポー側)

大きな通りの側道沿いにある建物「サンライズ船橋」の401号にあります。
メール・電話でも大丈夫です

「忙しく事務所へ行けない」という方にも、離婚の公正証書などの作成について、メールまたは電話により丁寧にサポートさせていただきます。


